夏バテと睡眠不足の関係とは?|明日からできる睡眠法
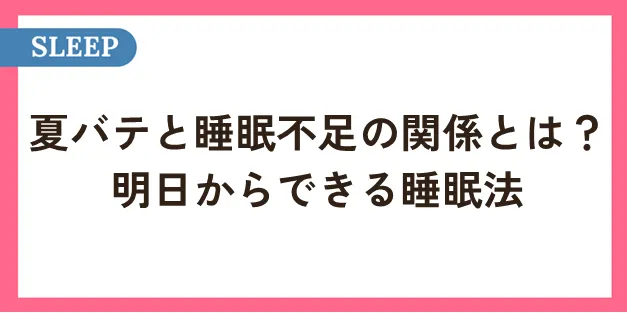
暑さが続く夏の夜、「なかなか寝つけない」「朝起きても疲れが取れていない」と感じることはありませんか?寝苦しさによる睡眠不足は、体のだるさや食欲不振、やる気の低下など、いわゆる夏バテの一因になることもあります。
暑さや湿度が原因で眠りの質が下がるこの季節こそ、意識的に睡眠環境を整えることが大切です。
本記事では、エアコンや寝具の工夫、入浴や食事のポイントなど、明日から実践できる夏の快眠術を紹介します。
夏バテと睡眠不足の関係
夏になると、だるさや食欲不振、やる気の低下など「夏バテ」と呼ばれる体調不良に悩まされる人が増えます。夏バテは医学的に明確な定義がないものの、慢性疲労や胃腸の不調、睡眠障害、ストレス症状などが複合的に現れるのが特徴です。自律神経の乱れが主な原因のひとつではないかと指摘されていますが、原因やメカニズムは解明されていません。
自律神経の乱れには、睡眠不足が大きく関わっている可能性があります。睡眠は季節に関係なく心身の回復に欠かせない要素であり、質の良い睡眠がとれない状態が続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなります。
夏は高温多湿や寝苦しさから睡眠が浅くなってしまいことがある、知らず知らずのうちに疲労が蓄積し、夏バテのような症状が現れることもあります。
そのため、夏バテを防ぐには、暑さ対策や栄養補給とともに、睡眠環境を整えることも重要です。
夏バテにつながる睡眠の特徴
睡眠不足は夏バテを引き起こす一因とされていますが、その背景には「質の低下した睡眠環境」が潜んでいることが少なくありません。とくに気温や冷房の使い方によって、身体に負担をかけるような眠りになってしまうケースは要注意です。ここでは、夏バテにつながりやすい睡眠環境の特徴を見ていきましょう。
●部屋が暑すぎる
夏の夜間に気温が25℃以上になると「熱帯夜」と呼ばれ、寝苦しさによって眠りが浅くなりがちです。睡眠中に体温が下がりにくくなると、入眠のリズムが乱れたり、途中で目が覚めたりと、十分な休息がとれなくなります。結果として、日中の疲労が抜けず、だるさや頭痛など夏バテの症状を引き起こす原因となります。
また、気づかないうちに室内で熱中症を発症する危険もあるため、夜間でも適度な温度管理が欠かせません。
●エアコンで部屋を冷やしすぎている
快適に眠ろうとエアコンを効かせすぎると、今度は身体が冷えすぎてしまう可能性があります。人の身体は汗をかいて熱を放出し、体温を調整する仕組みを持っていますが、過剰な冷房によってこの調整機能がうまく働かなくなると、自律神経の乱れを招きます。
特に首元やお腹が冷えると、だるさや胃腸の不調といった夏バテの症状が出やすくなります。
明日からできる!夏のぐっすり睡眠術
暑さで眠りが浅くなったり、寝苦しさから疲れが抜けにくくなったりする夏の夜を快適に過ごすには、睡眠の質を高める必要があります。
明日から実践できる「夏の快眠対策」を紹介します。
●エアコンを正しく使用する
快適な室温を保つためには、エアコンを正しく使う必要があります。環境省では、省エネルギーと快適性を両立する目安として、夏は室温28℃を推奨しています(これは設定温度ではなく、室内の実際の温度を指します)。
ポイントは、冷やしすぎを防ぎつつ、空気を穏やかに循環させることです。エアコンの風が直接身体に当たると、皮膚表面が冷えすぎて体温調整機能が乱れ、自律神経のバランスにも影響を及ぼします。
さらに、サーキュレーターや扇風機を併用することで空気の流れをつくると、冷気が滞留せず室温が均一になりやすくなります。
●寝具を工夫する
夏の寝具選びは、心地よい「寝床内気象」を保つために重要です。理想とされるのは、温度32〜34℃、湿度45〜55%です。この状態を目指すために、通気性や接触冷感性に優れた寝具を活用しましょう。
おすすめは、通気性や吸湿・放湿性に優れた素材を取り入れることです。たとえば、麻やリネン、ガーゼ素材は熱がこもりにくく、湿気を逃してさらりとした肌触りが続くため、寝返りを打ったときの不快感が少なくなります。
また、接触冷感素材を使ったパッドシーツや枕カバーも人気です。ただし、冷感素材は汗を吸いにくいものもあるため、吸湿性の高いインナーシーツやタオルケットとの併用が大切です。
●寝る1~2時間前に入浴する
深部体温(体の内側の温度)は、日中に高くなり、夜間に下がるリズムで調整されています。眠気は体温が下がり始めるタイミングで訪れるため、入浴によって一度体温を上げ、自然な放熱を促すことでスムーズな入眠が可能になります。
とくに就寝の1〜2時間前にぬるめのお湯に浸かるのが効果的とされており、リラックス効果も相まって快眠につながります。
●適切な食事をとる
体内時計を整えるためには、食事のタイミングと内容も大切です。朝食は1日のリズムをスタートさせる重要な役割があり、食事をとらないと寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりするおそれがあります。
また、夜遅くの間食や過度な塩分摂取も要注意です。夜食は消化器官を休ませずに睡眠を妨げる原因となり、塩分の摂りすぎは夜間の排尿回数を増やして中途覚醒を招きます。就寝前はなるべく胃腸に負担をかけない、軽めの食事を心がけましょう。
●寝る前にリラックスできる時間をつくる
質の高い眠りをとるには、「眠る前の過ごし方」が重要です。体には、日中に活動し、夜になると自然と眠気を感じる「体内時計」が備わっています。このリズムを整えるうえで重要なのが、交感神経と副交感神経の切り替えです。
現代人は、スマートフォンやパソコンなどの強い光や情報の刺激を就寝直前まで受けやすく、脳や神経が高ぶったまま眠りにつこうとしてしまうことがあります。その結果、寝つきが悪くなったり、夜中に目覚めやすくなったりします。
そこでおすすめなのが、就寝の1時間ほど前から自分を休息モードへ導く習慣を持つことです。たとえば、照明を少し落としてぬるめのハーブティーを飲む、ストレッチで身体をゆるめる、心地よい音楽やアロマを取り入れるなど、五感を落ち着かせるルーティンが効果的です。メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌を促し、眠気を引き出してくれます。
まとめ|夏バテ知らずの快眠習慣を、今日から少しずつ
暑さが続く夏の夜は、ただ寝るだけでもひと苦労。けれども、睡眠の質が落ちると、疲労やストレス、自律神経の乱れにつながり、結果として「夏バテ」のような不調を招きやすくなります。
だからこそ、エアコンの使い方や寝具の工夫、就寝前の過ごし方など、ほんの少しの意識と準備が大切です。
今日からできる3つのアクション
- 就寝の1〜2時間前にぬるめのお風呂に入り、深部体温を自然に下げる準備をする
- 寝具は通気性の良い冷感素材や麻素材に衣替えし、寝苦しさを軽減する
- 朝はしっかり朝食をとり、日光を浴びて体内時計を整える習慣をつける
よく眠れるだけで、夏バテの影響を抑えることができます。今回、解説した内容を参考に快適な睡眠環境を作り、夏バテ知らずの生活を目指しましょう。
💬 みんなで語ろう:「【テーマトーク】夏の夜、ぐっすり眠れてる?」はこちら
参考情報




