酪酸の効果とは?腸内環境維持と免疫力を高める理由
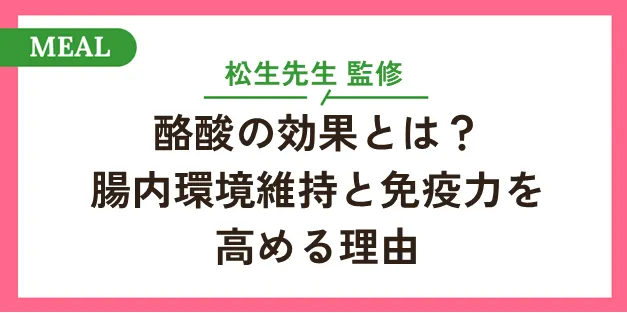
「酪酸(らくさん)」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?この小さな脂肪酸こそ、腸の健康と全身の免疫力を陰で支える、まさに“腸内エネルギー源”なのです。
酪酸とは?—大腸を動かす重要なエネルギー
酪酸は「短鎖脂肪酸」の一種で、大腸内に棲む善玉菌が食物繊維を発酵分解する過程でつくり出されます。
私たちの体では消化・吸収できない食物繊維を、腸内細菌が“発酵”させ、その副産物として酪酸が生まれるのです。
この酪酸は、大腸の粘膜細胞にとって最大のエネルギー源。
小腸のエネルギー源がグルタミンであるのに対し、大腸では酪酸がその働きを担っています。
つまり、食物繊維がなければ、腸は本来の力を十分に発揮できないということです。
🔗関連記事:グルタミンとは?条件付き必須アミノ酸と言われる理由
酪酸が腸と免疫力を高める理由
酪酸が腸内でしっかり生成されると、大腸の粘膜は活発に働き、腸内のpHが酸性に保たれます。
これにより、悪玉菌が棲みにくくなり、善玉菌が優勢な腸内環境が維持されます。
その結果、腸内環境の改善だけでなく、全身の免疫力アップにもつながるのです。
食べ物から「酪酸」を摂っても意味がない?
実は、酪酸自体はバターやチーズなどに含まれています。しかし、食事から摂取した酪酸は腸内の酪酸量にはほとんど影響しません。重要なのは、「腸の中で酪酸をつくること」です。
その鍵を握るのが「酪酸産生菌」。これらの菌は、食物繊維以外にも、オリゴ糖・レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)を“エサ”として酪酸をつくり出します。
食物繊維の真のチカラ
かつては「栄養にならないカス」と誤解されていた食物繊維。
しかし今では、その健康効果が科学的に認められ、腸内環境の改善、生活習慣病の予防など、さまざまな面で注目されています。
特に注目すべき4つの作用はこちらです。
- 保湿性:水分を吸って便をやわらかくし、便通を促進
- 粘性:ゲル状になり消化管内をゆっくり移動。血糖値やコレステロールの急上昇を抑える
- 吸着性:有害物質や余分なコレステロールを排出(=デトックス効果)
- 発酵性:大腸の善玉菌によって発酵され、酪酸などの有機酸を生成。腸内を酸性に保ち、環境を整える
不溶性と水溶性のバランスがカギ
「野菜をたくさん食べているのに便秘が改善しない」という方は、不溶性食物繊維に偏っている可能性があります。
便のかさを増やす不溶性と、水分を吸収して便をやわらかくする水溶性を2:1のバランスで摂ることが理想的です。
特に不足しがちな水溶性食物繊維は以下の食品に豊富です。
- 大麦、もち麦
- 海藻類(わかめ、昆布、もずくなど)
- きのこ類(なめこ、しいたけ)
- ネバネバ食材(オクラ、長いも)
- 果物(アボカド、キウイなど)
最後に:酪酸は“腸の未来”を守る成分
腸内環境は、私たちの健康状態や免疫力、さらには気分やメンタルバランスにまで影響を与えることが分かってきています。
酪酸は、その腸の健やかさを支える“縁の下の力持ち”です。
今、何を食べるかが、未来の自分をつくる。
今日から食物繊維を意識して摂り、腸内で“自家発電”できる体を育てていきましょう。
監修:松生恒夫1995年東京生まれ。医学博士。松生クリニック院長。東京慈恵会医科大学卒業。同大学第三病院内科助手、松島病院大腸肛門病センター診療部長などを経て、2003年、東京都立川市に松生クリニックを開業。6万件以上の大腸内視鏡検査を行ってきた腸疾患治療の第一人者。便秘外来の専門医として地中海式食生活、漢方治療、音楽療法などを取り入れた診療で効果を上げている。著書に『子どもの便秘は今すぐなおせ』(主婦の友社)、『見た目は腸が決める』(光文社)、『「腸の老化」を止める食事術』(青春出版社)、『日本一の長寿県と世界一の長寿村の腸にいい食事」(PHP研究所)など多数。 ■松生クリニックHP https://matsuikeclinic.com |




