亜鉛の効果とは?腸のバリア機能を支える亜鉛の秘密
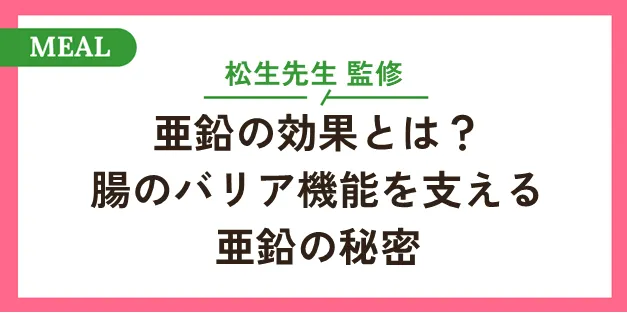
「亜鉛」と聞くと、「味覚に関係する栄養素」や「免疫力に関わる成分」として耳にしたことがある方も多いかもしれません。でも実はこの亜鉛、腸の健康とも深い関わりがあることをご存知でしょうか?
私たちの腸は、食べ物から栄養を吸収するだけでなく、体を外敵から守る“バリア”のような役割も果たしています。そして、この見えないバリアを支えているのが、まさに亜鉛なのです。
亜鉛は体の中でどんな役割をしている?
亜鉛は、鉄に次いで体内に多く存在する必須ミネラルのひとつで、細胞の働きを助ける酵素やたんぱく質のサポート役として幅広く活躍しています。体の中で新しい細胞がつくられたり、傷が治ったり、免疫機能が働いたりする場面では、いつも亜鉛が関わっています。
特に、私たちの腸の内側にびっしりと並ぶ細胞(腸管上皮細胞)がしっかり機能するためにも、亜鉛は欠かせません。
「腸のバリア機能」を支える亜鉛
腸の内側には、外から侵入する細菌やウイルス、未消化の食べ物、有害物質などから体を守る“バリア”が存在しています。これは、腸管上皮細胞同士がぴったりと隙間なくくっつき、いわば“レンガの壁”のように外敵をブロックしていることで成り立っています。
この細胞のつながりをしっかり保つために必要なのが、まさに亜鉛です。亜鉛は、細胞が健康な状態で再生したり、細胞同士の結びつきを強くしたりするために働きます。これにより、腸のバリアが壊れにくくなり、体の中に余計なものが入り込むのを防いでくれるのです。
亜鉛が不足するとどうなる?
現代の食生活では、亜鉛不足が起きやすいと言われています。加工食品や偏った食事、ストレス、飲酒などが続くと、体内の亜鉛が消耗されたり、吸収されにくくなったりするためです。
亜鉛が不足すると、以下のような不調が現れることがあります。
- 味覚の低下(味がしにくくなる)
- 肌荒れや髪のトラブル
- 免疫力の低下で風邪をひきやすくなる
- お腹の調子が乱れる
とくに腸のバリア機能が弱まると、「リーキーガット(腸漏れ)」と呼ばれる状態になり、アレルギーや慢性疲労、肌荒れなど、思わぬ不調につながることもあります。
食事でしっかり亜鉛をとろう
亜鉛を多く含む食品には、以下のようなものがあります。
- 牡蠣(かき)
- 牛肉
- レバー
- 卵
- ナッツ類(アーモンド、カシューナッツなど)
- 納豆、味噌などの発酵食品
こうした食材を日々の食事に取り入れることで、腸だけでなく全身の健康を守る土台をつくることができます。
まとめ:腸を守る“名脇役”、それが亜鉛
私たちの体の中で、黙々と働き続けている亜鉛。見えないけれど確かに存在する腸のバリアを支え、日々の健康を下支えしてくれている存在です。腸の不調を感じている方、肌や免疫が気になる方は、一度「亜鉛」に目を向けてみるのもよいかもしれません。
監修:松生恒夫1995年東京生まれ。医学博士。松生クリニック院長。東京慈恵会医科大学卒業。同大学第三病院内科助手、松島病院大腸肛門病センター診療部長などを経て、2003年、東京都立川市に松生クリニックを開業。6万件以上の大腸内視鏡検査を行ってきた腸疾患治療の第一人者。便秘外来の専門医として地中海式食生活、漢方治療、音楽療法などを取り入れた診療で効果を上げている。著書に『子どもの便秘は今すぐなおせ』(主婦の友社)、『見た目は腸が決める』(光文社)、『「腸の老化」を止める食事術』(青春出版社)、『日本一の長寿県と世界一の長寿村の腸にいい食事」(PHP研究所)など多数。 ■松生クリニックHP https://matsuikeclinic.com |




