口腔内細菌が全身の病気引き起こす?主な病気と対処法
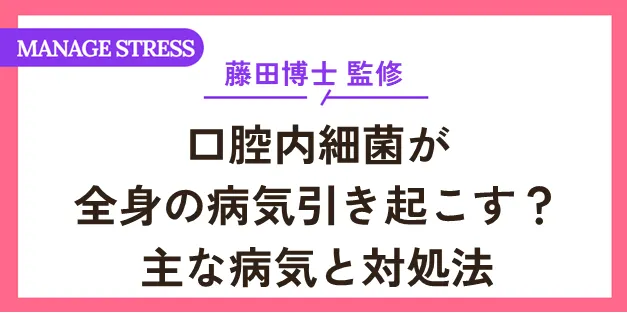
口腔内細菌とは?私たちの口の中は「細菌のコロニー」
人間の口の中には、約700種類以上の細菌が存在しており、これらは「口腔常在菌」として知られています。健康な人でも1,000億個以上の細菌が共存していると言われ、まさに“細菌のエコシステム”が口の中に存在しています。
そのバランスが崩れることで虫歯や歯周病といった口腔トラブルだけでなく、全身の健康にまで悪影響を及ぼすことが最新の研究でわかってきました。
口腔内細菌が引き起こす病気とは?
●虫歯・歯周病
これは多くの人が知っている基本的な影響です。ミュータンス菌が虫歯を引き起こし、ポルフィロモナス・ジンジバリス(P. gingivalis)などが歯周病の原因菌として知られています。
●心臓病や脳梗塞
近年注目されているのが、歯周病菌が血流に乗って血管壁、心臓や脳に到達し、動脈硬化・心筋梗塞・脳卒中のリスクを高めるという研究結果です。
●認知症との関連
アルツハイマー型認知症の患者の脳内から、歯周病菌由来の毒素(ジンジパイン)が検出されたという報告があり、口腔内細菌が脳に悪影響を及ぼす可能性が示唆されています。
●糖尿病の悪化
歯周病は慢性炎症を引き起こすため、インスリン抵抗性を悪化させるというメカニズムがあるとされ、糖尿病との“相互関係”があることがわかっています。
なぜ「口の中」が全身に影響を与えるのか?
ポイントは、歯ぐきの炎症による血管の“入口”ができること。そこから細菌や炎症物質が全身に広がり、さまざまな疾患の引き金になります。
つまり、「歯ぐきの出血」は“血管の傷口”=体内をめぐる血液への侵入口であり、放置すればするほどリスクが拡大します。
口腔内細菌バランスを整える方法
●歯科での定期検診とクリーニング
年に2回ほど、歯医者さんでプロのケアを受けましょう。お口の中をチェックしてもらいながら、すみずみまできれいにしてもらうことで、トラブルの予防につながります。
●毎日の歯磨き習慣を見直してみましょう
歯磨きは「1日2回以上」が基本。フロスも取り入れると、歯と歯の間もすっきり。とくに寝る前は、ゆっくり丁寧にケアすると安心です。
●食生活を整える
甘いものを控えめにして、発酵食品やオメガ3脂肪酸(青魚やナッツ類など)を意識してとることで、善玉菌が増えやすい環境づくりに役立ちます。
●口呼吸を減らして鼻呼吸を意識
口で呼吸するとお口の中が乾きやすくなり、菌のバランスが崩れやすくなります。ふだんの呼吸が「口呼吸」になっていないか、ぜひチェックしてみてくださいね。
まとめ:健康の入口は「口の中」から始まる
口腔内細菌はただの“虫歯の原因”ではありません。全身の健康と深く結びついた存在です。今後ますます医療の世界では「口と体の連携」が重視されていくでしょう。
日々の歯磨きや食生活の見直しが、10年後の健康を守る大きな投資になるのです。
参考情報
監修:藤田孝輝1960年生まれ。理学博士。1985年山形大学大学院農学研究科修了後、塩水港精糖㈱入社。在籍中に乳糖果糖オリゴ糖製造酵素生産菌を発見。この発見は、家庭用オリゴ糖類食品の国内での普及に大きく貢献。同社糖質研究所研究室長、研究所長を経て、同社常務取締役生産開発グループ長、関西製糖㈱代表取締役社長を歴任。山形大学・日本大学・園田学園女子大学・熊本大学・愛国学園短期大学にて非常勤講師も務めるなど、教育活動にも携わる。現在は塩水港精糖㈱理事・糖質研究所長、日本応用糖質科学会理事を務める。 |




