乳酸菌とビフィズス菌の違いとは?特徴について解説
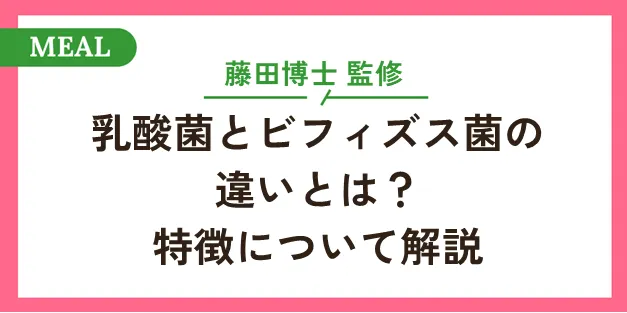
ヨーグルトや乳酸菌飲料のCMでよく耳にする「乳酸菌」や「ビフィズス菌」。どちらも“腸にいい菌”として知られていますが、「何がどう違うの?」と疑問に思ったことはありませんか?
このコラムでは、乳酸菌とビフィズス菌の違いと、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。
どちらも“善玉菌”、でも別の仲間
まず押さえておきたいのは、“乳酸菌とビフィズス菌は、どちらも腸内環境を整える「善玉菌」”であるという点。ですが、実は分類上はまったく別の細菌なのです。
- 乳酸菌は、「糖を分解して乳酸をつくる菌」の総称で、ラクトバチルス属(Lactobacillus)やストレプトコッカス属(Streptococcus)などが代表的。
- ビフィズス菌は、ビフィドバクテリウム(Bifidobacterium)という別の属に分類され、乳酸菌には含まれません。
同じように“乳酸を作る”ことから混同されがちですが、分類学的には全く異なる菌です。
活躍する場所も違う ~その理由は「酸素」にあった~
乳酸菌とビフィズス菌は、腸内の住みかも異なります。
- 乳酸菌は主に小腸で活躍
- ビフィズス菌は主に大腸で働く
この違いには、「酸素の存在」が関係しています。
乳酸菌の多くは通性嫌気性菌(酸素があってもなくても生きられる菌)であり、酸素が比較的多く存在する小腸でも生存・活動が可能です。
一方で、ビフィズス菌は偏性嫌気性菌(酸素があると生きられない菌)であり、酸素がほとんど存在しない大腸に適しているのです。
つまり、それぞれの菌は「酸素環境の違い」に応じて、自分が生きやすい腸内のエリアで活躍しているというわけです。
作り出す“酸”も違う
乳酸菌がつくるのは主に「乳酸」。この乳酸が腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑える働きをします。
一方、ビフィズス菌は「乳酸」と「酢酸」をつくります。特に酢酸は腸内をより酸性に保ち、腸のバリア機能を高める効果があると注目されています。近年では、この酢酸の抗炎症作用や感染防御への働きも研究されています。
乳児の腸はビフィズス菌だらけ?
ビフィズス菌は、赤ちゃんの腸内に最も多く存在する菌としても知られています。特に母乳で育てられた赤ちゃんはビフィズス菌が豊富。加齢とともにその割合は減っていきます。
一方で、乳酸菌は大人になってからもさまざまな食品からとりやすく、食生活に取り入れやすい善玉菌です。
どっちがいい? 答えは「両方とるのがベスト」
乳酸菌とビフィズス菌は、どちらか一方だけではなく、両方とることで腸内のバランスをより良く保てると言われています。さらに、菌の“エサ”となるオリゴ糖や食物繊維を一緒にとることで、これらの善玉菌が元気に働きやすくなります。
このように「善玉菌+そのエサ」をセットでとる方法は、「シンバイオティクス」とも呼ばれ、腸活の新常識になりつつあります。
乳酸菌とビフィズス菌はこんな食品から
- 乳酸菌:ヨーグルト、チーズ、味噌、ぬか漬け、キムチ、甘酒などの発酵食品
- ビフィズス菌:ビフィズス菌入りと表示されたヨーグルトや発酵乳、ビフィズス菌配合サプリメント
日常の食事にこうした食品をバランスよく取り入れることで、両方の善玉菌を効率よく補うことができます。
まとめ:違いを知って、菌活をもっと楽しく
- 乳酸菌=酸素にも強く、小腸で乳酸をつくって活躍
- ビフィズス菌=酸素が苦手で、大腸で乳酸と酢酸をつくってバリアを守る
- どちらも腸の味方。違いを知って賢く取り入れましょう
ヨーグルト、発酵食品、サプリメントなど、日常の食事の中に上手に取り入れて、今日から楽しく「菌活」始めてみませんか?
監修:藤田孝輝1960年生まれ。理学博士。1985年山形大学大学院農学研究科修了後、塩水港精糖㈱入社。在籍中に乳糖果糖オリゴ糖製造酵素生産菌を発見。この発見は、家庭用オリゴ糖類食品の国内での普及に大きく貢献。同社糖質研究所研究室長、研究所長を経て、同社常務取締役生産開発グループ長、関西製糖㈱代表取締役社長を歴任。山形大学・日本大学・園田学園女子大学・熊本大学・愛国学園短期大学にて非常勤講師も務めるなど、教育活動にも携わる。現在は塩水港精糖㈱理事・糖質研究所長、日本応用糖質科学会理事を務める。 |




